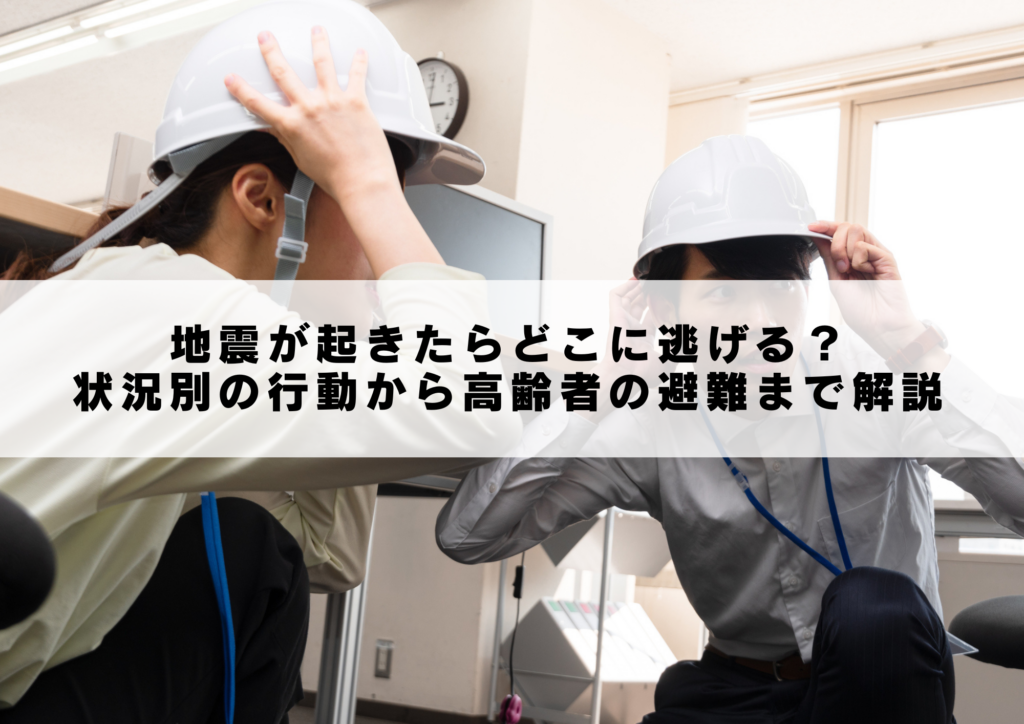
地震が起きたときにどこに逃げるのか迷った経験はありませんか。また、避難方法についても不安に感じることがあるでしょう。
本記事では、状況別の正しい避難場所や、介護の現場で欠かせない高齢者の避難のポイントを解説します。夜間の注意点など避難に関するよくある質問にも具体的にお答えしていきます。
この記事を読めば、大切な人の命を守るための知識が身につきますので、ぜひ最後までご覧ください。
地震が起きたらどこに逃げる?状況別の行動
職場や自宅、屋外といった場面ごとに、命を守るための最適な行動は異なります。ここでは、状況に応じた避難方法を解説します。
揺れている最中は机の下など頑丈な場所へ
地震の揺れを感じたら、落下物や転倒物から頭や体を守ることが最優先です。大きな揺れは、棚の物が落ちたり家具が倒れたりする危険を引き起こします。
自宅や職場では、机の下にしっかりと体を収め、手で首筋を守る姿勢を取りましょう。この姿勢は頭や首筋を守るだけでなく、体への衝撃も和らげる効果が期待できます。
スーパーなどにいる場合は、商品棚やショーケースからすぐに離れてください。柱や階段の踊り場が比較的安全です。
揺れている最中は、慌てて動こうとせず、その場で身を守ることを第一に考えましょう。
自宅では玄関や柱の多い安全な空間へ
ご自宅で大きな揺れを感じた場合は、玄関や柱の多い安全な空間に移動しましょう。これらの場所は、建物の中でも比較的構造が強く、家具が少ないため倒れてくる物による危険が少なくなります。
また、玄関は避難経路を確保するのに役立つため、揺れを感じたらすぐにドアを開けておきましょう。そのあとは、頭を守る姿勢で揺れが収まるのを待ちます。
いざというときに備え、ご家庭内で安全な場所をあらかじめ確認しておくことが重要です。
職場や介護施設では指示に従い指定場所へ
職場や介護施設では、個人の判断で動かず、防災担当者や責任者の指示に従うことが最も重要です。多くの人がいる場所でそれぞれが行動すると、混乱が大きくなり危険です。
特に介護施設では、職員が冷静さを保ち、利用者の安全を最優先に行動しなくてはなりません。ご自身の安全を確保してから、利用者の状態に応じて適切な声かけや介助を行いましょう。
すぐに避難誘導が難しい場合は、布団などで頭を守ってもらうことも有効な手段です。日頃から訓練で決められた役割を思い出し、周りの職員と協力して組織的に動くことが大切です。
屋外では公園や広場など開けた場所へ
屋外で地震にあった場合は、公園や広場、運動場など、落下物の危険がない広い場所へ移動しましょう。ただし、揺れている最中に無理に移動すると危険ですので、その場でしゃがんで身を守り、揺れが収まってから安全な場所に向かってください。
また、ビルの壁や看板、窓ガラス、ブロック塀や自動販売機などには近づかないように注意しましょう。普段から、外出時には周囲の安全な場所を意識しておくと安心です。
参考:東京防災ホームページ『外出時の行動マニュアル(地震発生時)』
高齢者の避難で知っておくべき3つのポイント

高齢の方を安全に避難させるには、特別な配慮が必要です。ここでは、いざというときに高齢者の命を守るために大切な3つのポイントを解説します。
的確な避難タイミングの判断
高齢者の避難では、危険が迫る前のタイミングで行動を開始することが重要です。移動に時間がかかるため、判断が少しでも遅れると逃げ遅れてしまう危険性が高まります。
大きな揺れが収まったら、すぐにラジオやスマートフォンで公式の情報を集めましょう。SNSでは誤った情報が拡散されることもあるため、できるだけ公的機関の発表や信頼できる情報源をもとに状況を判断することが大切です。
日頃からどのような状況になったら避難を始めるか、職場内で基準を話し合っておくと安心です。
安全な避難経路と介助方法の事前確認
災害時に慌てず行動するため、安全な避難経路と介助方法を事前に確認しておきましょう。いざというときに、普段通れる道が使えなくなっている可能性があります。
施設から避難場所までの道を実際に歩き、ブロック塀や斜面といった危険な箇所を避けたルートを複数設定しておくと安心です。施設内には避難経路図を掲示し、職員全員がいつでも確認できるようにします。
避難訓練では、車いすの方や寝たきりの方をどう誘導するかなど、具体的な介助方法を確認し合うことが大切です。事前の入念な準備と訓練の積み重ねが、利用者と職員自身の安全を守ることにつながります。
日頃からの綿密なコミュニケーション
災害時に迅速な連携を取るため、日頃から職員間や関連機関とのコミュニケーションを大切にしましょう。緊急時に初めて連絡を取り合っても、混乱してうまく機能しない可能性が高いからです。
施設内では、誰が指揮を執るのか、それぞれの職員の役割は何かを事前に明確にしておくことが重要です。ご家族や医療機関への連絡方法も、緊急連絡網として整備しておきましょう。
施設の中だけでなく、家庭や地域とも普段からつながりを持っておくことが、いざというときの助け合いを生むのです。
関連記事:介護施設の非常災害時の対応|準備から避難訓練まで徹底解説
地震の避難に関するよくある質問
地震の避難について、いざというときどうすべきか迷うことも多いでしょう。ここでは、避難に関するよくある質問を取り上げます。
屋内と屋外ではどちらがより安全?
どちらが安全かは、建物がどれだけ頑丈かによって変わります。耐震性の高い新しい建物にいる場合は、屋内の方が安全です。慌てて外に出ず、玄関や柱の多い部屋で揺れが収まるのを待ちましょう。
一方で、古い木造住宅など倒壊の恐れがある建物にいる場合は、屋外へ避難する方が命を守れる可能性が高まります。その際は、看板やガラスなどの落下物に十分注意してください。公園や広場といった、周りに何もない開けた場所を目指しましょう。
ご自宅や職場など、普段過ごす建物の耐震性を意識しておくことが、いざというときの判断に役立ちます。
夜間に地震が発生した場合の注意点は?
夜間に地震が起きた際は、まず照明と足元の安全を確保することが大切です。停電で真っ暗な中、慌てて動くと割れたガラスなどで足を怪我する危険があるためです。
揺れが収まったら、すぐに懐中電灯やスマートフォンのライトをつけて周りを確認しましょう。室内が散乱していることを想定し、必ず靴やスリッパなどを履いてから移動を開始してください。
もし停電していたら、復旧時の火災(通電火災)を防ぐために、ストーブなどの電源コードを抜いておくと安心です。普段から枕元にライトと室内履きを準備しておくことを強くおすすめします。
ペットと一緒に避難することはできる?
現在では、ペットと一緒に避難所へ向かう「同行避難」が推奨されるようになっています。しかし、自治体によってはペット連れの避難を認めていない場合もあります。事前に、住んでいる地域でペットの受け入れが可能かを確認しておきましょう。
同行避難ができる場合でも、多くの避難所で人とペットの居場所は分けられます。そのため、普段からペットがケージに入ることを練習しておくと安心です。非常時のペットフードや水、迷子札なども備えておきましょう。
まとめ
職場でも家庭でも、命を守るための基本は「事前の備え」と「冷静な判断」です。特に介護の現場では、職員同士の連携と早めの行動が、利用者の安全に直結します。
本記事で得た知識を、ぜひ職場の防災体制の見直しや、ご家族との防災会議に役立ててください。今日から、枕元にライトとスリッパを置いたり、ご家族と災害時の連絡方法を確認したりすることから始めてみましょう。
こうした確実な備えが、いざというときに冷静に大切な人を守る自信につながります。
関連記事
防災⼠の詳細はこちら
証券会社勤務後、広告代理店兼防災用品メーカー勤務。経営管理部を立ち上げ、リスクマネジメント部を新たに新設し、社内BCP作成に従事。個人情報保護、広報(メディア対応)、情報システムのマネジメント担当。NPO事業継続推進機構関西支部(事業継続管理者)。レジリエンス認証の取得、更新を経験。レジリエンス認証「社会貢献」の取得まで行う。レジリエンスアワードとBCAOアワードの表彰を受ける。現在では、中小企業向けBCP策定コンサルティング事業部を立ち上げ、コーディネーターとして参画。
関連記事
-
介護施設
2026/01/23
冬の入浴介助の注意点|事故を防ぐ事前準備から緊急時の対応…

西條 徹
-
介護BCP
2026/01/16
地震のとき必要なもの|企業の備蓄義務・備蓄リスト・管理策…

西條 徹
-
介護施設
2026/01/09
介護施設のユニット目標例を紹介|目標作成の手順から振り返…

西條 徹
-
介護施設
2025/12/26
大量の書類の保管方法|監査で焦らない介護記録の整理術

西條 徹
-
介護施設
2025/12/12
新人教育で自分の仕事ができない!原因と3つの解決策を徹底…

西條 徹
-
介護BCP
2025/12/05
震度5弱と5強の違いは?5と6だけ弱・強がある理由から備…

西條 徹


