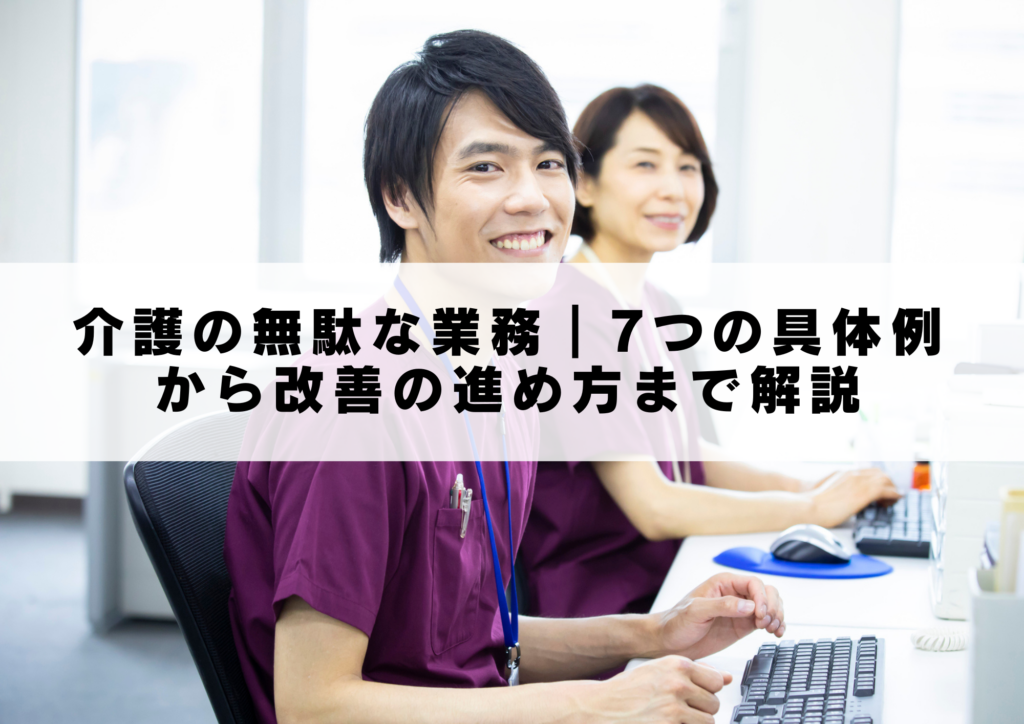
「日々の業務に追われるばかりで、介護の質が落ちてしまうのではないか……」そんな不安を抱えていませんか?記録や会議に時間を取られ、職員の笑顔が減っているとしたら、それは職場に潜む「無駄な業務」が原因かもしれません。
本記事では、多くの介護施設に共通する7つの無駄な業務と、明日から実践できる具体的な改善の進め方、活動でつまずきがちな疑問への答えをまとめました。
この記事を読めば、あなたの施設で今すぐ取り組める業務効率化のヒントが明確になります。職員の負担を減らし、チームの活気を取り戻して、質の高いケアを提供できる職場づくりを始めましょう。
介護現場の無駄な業務7選
あなたの施設にも、気づかないうちに職員の負担を増やしている業務が隠れているかもしれません。日々の忙しさの中で当たり前になっている作業も、改善できる可能性があります。
ここでは、多くの介護現場で共通して見られる7つの無駄な業務を紹介します。
時間のかかりすぎる記録と書類作成
毎日の記録や書類の作成に、多くの時間を使いすぎていないでしょうか。手書きでの作業や、同じ内容を何度も転記する作業は、改善できる業務の代表例です。
手書きでの記録には特に時間がかかり、1回の記録に15分ほど、1日に合計1時間近くを費やす場合もあります。たとえば、バイタル測定の結果をメモし、それを清書して、さらにパソコンへ入力するような作業です。
このような時間は、介護ソフトを導入すると大幅に短縮できます。タブレット端末を使えば、その場で入力が完了し、職員の負担を大きく減らすことにつながります。
目的があいまいで長引く会議や申し送り
目的がはっきりしないまま始まって、長引いてしまう会議や申し送りも、職員の時間を奪う原因になります。チームでの情報共有は不可欠ですが、その方法を見直す必要があります。
会議の途中で話がそれてしまったり、いつも同じ内容を形式的に確認したりするだけでは、新しい成果は生まれません。介護記録を読めばわかる内容を、口頭の申し送りで繰り返すのも非効率です。
会議の目的を明確にし、本当に必要な人だけが参加するようにしましょう。インカムなどのICT機器を活用すれば、リアルタイムで情報を共有でき、申し送りの時間も短くなります。
重複している情報共有と確認作業
職員間の情報共有がうまくいかないと、同じ確認作業が何度も発生し、業務の効率を下げてしまいます。職種間の連携不足が、見えにくい無駄を生んでいる可能性があります。
たとえば、介護職員と看護職員が、それぞれ別のタイミングで利用者に同じ質問を繰り返してしまうような状況です。重複した確認は、以下のような問題を引き起こします。
- 利用者にストレスを与えてしまう
- 職員の作業時間が無駄になる
- 連絡ミスからトラブルに発展する
口頭でのあいまいな指示も、確認の手間を増やす原因です。ICTツールで情報を一元化したり、記録のルールを統一したりすると、スムーズな連携が実現します。
優先順位が不明確で手戻りが多いタスク
日々の業務に追われる中で、作業の優先順位があいまいになっていないでしょうか。今やるべきことを見誤ると、非効率な状況を生み出し、時間を浪費してしまいます。
忙しい状況では、つい目の前の作業から手をつけてしまいがちです。しかし、本来優先すべき業務が後回しになると、利用者を待たせてしまい、不満につながる可能性もあります。
業務を始める前に、やるべきことをリストアップし、優先順位を明確にすると、計画的に仕事を進められるようになります。
必要以上に時間をかけたケアや介助
ケアや介助の進め方が非効率なために、本来よりも多くの時間がかかっている場合があります。業務の進め方が職員個人の経験に頼っていると、無駄が生まれやすくなります。
準備不足も、時間を浪費する大きな原因です。たとえば、排せつ介助の際に必要な物品がそろっておらず、何度も物を取りに戻るような場面が考えられます。
スケジュールを厳格に決めすぎると、予定より早く終わったときに手待ち時間が発生します。介助しやすい環境を整えると共に、空き時間に行える作業リストを用意しておくと、時間を有効に活用できるでしょう。
作成に時間がかかる複雑なシフト表
職員の勤務シフト表の作成は、特にリーダー職にとって大きな負担となりがちな業務です。職員一人ひとりの希望や公平性を考えながら作成するには、多くの時間と手間がかかります。
手書きで作成している場合、書き間違えが起きると最初からやり直しになることもあります。複雑な条件をパズルのように組み合わせる作業に、毎月多くの時間を費やしているのではないでしょうか。
シフト上の問題が、現場の非効率を生んでいる場合もあります。シフト作成ソフトやアプリを活用すると、作成者の負担が軽くなるだけでなく、ミスも減らせます。
アナログな備品管理と発注作業
備品の管理や発注作業が非効率だと、本来の介護業務に集中する時間を奪ってしまいます。必要なものを探す時間は、業務の流れを止めてしまう無駄な時間です。
在庫数がきちんと把握できていないと、必要なときに備品が足りなくなったり、逆に余分に発注してしまったりする無駄も生まれます。担当者がいないと発注できず、業務が滞ることも考えられます。
いざというときにオムツが見つからず、倉庫まで探しに行くような状況は改善が必要です。職場環境を整え、備品の置き場所や発注のルールを決めておくだけでも、こうした無駄な時間を減らせます。
無駄をなくす業務改善の進め方

現場に潜む無駄な業務を特定できたら、次はいよいよ具体的な改善策を進める段階です。しかし、やみくもに手をつけてもうまくいきません。
職員全員で課題を共有し、順序立てて取り組むことが成功につながります。ここでは、業務改善を進めるうえで役立つ視点を解説します。
関連記事:介護施設の業務改善事例|改善の進め方もあわせて解説
3M(ムリ・ムダ・ムラ)の視点で課題を捉える
業務改善を始めるときは「ムリ・ムダ・ムラ」の3つの視点で課題を整理するのが効果的です。この考え方を使うと、漠然とした問題点がはっきりします。
これらは介護の質を下げる原因にもなりうる以下の3つの状態を指します。
- ムリ:職員の能力を超える過度な負担
- ムダ:本来は省略できる不要な作業
- ムラ:業務のやり方や質にばらつきがある
たとえば、新人職員に過重な業務を任せるのは「ムリ」、同じ内容を何度も記録するのは「ムダ」です。職員によってケアの方法が異なり、利用者が不安を感じるのは「ムラ」にあたります。
業務の棚卸しで不要な作業を見える化する
職員の感覚だけに頼らず、客観的なデータで不要な作業を「見える化」することが、業務改善では欠かせません。「何にどれくらい時間がかかっているか」を正確に把握すると、的確な改善策を立てられます。
まずは、一日に行っている業務を細かく書き出してみましょう。そして、それぞれの作業にかかる時間を記録していきます。10〜15分単位で記録すると、業務が集中する時間帯などが一目でわかります。
厚生労働省が提供する「課題把握シート」の活用もおすすめです。業務を書き出して整理すると、削減できる作業や見直すべき業務の流れが具体的に浮かび上がってきます。
参考:厚生労働省『ツール集』
ICTツールを活用し業務を自動化する
業務の棚卸しで見つかった課題を解決する手段として、ICT(情報通信技術)ツールの活用は非常に有効です。人の手では時間のかかる作業を、ツールの力で効率化できます。
これにより、職員は本来時間をかけるべき利用者へのケアに、より多くの時間をあてられるようになります。たとえば、介護ソフトを導入すれば記録業務の手間が減り、インカムを使えばリアルタイムで情報共有が可能です。
見守りシステムは、夜勤スタッフの心身の負担を軽くします。IT導入補助金のような制度を利用すると、費用負担を抑えながら導入も可能です。あなたの施設に合ったツールを探してみましょう。
介護の業務改善に関するよくある質問
業務改善を進めようとすると、職員の反応や予算の問題など、さまざまな壁にぶつかることがあります。
ここでは、業務改善を進める際によくある3つの質問に答えます。
ICTが苦手な職員へのフォロー方法は?
ICT機器の操作に苦手意識をもつ職員がいるのは、ごく自然なことです。大切なのは、なぜ導入するのかという目的を共有し、組織として丁寧にサポートする体制を整えることです。
「あなたの仕事が楽になる」というメリットを本人が実感できると、操作への抵抗感は薄れていきます。また、安全に使うための研修を実施すれば、安心して新しい技術に向き合えます。
現場の意見を聞く場を設けたり、音声入力のような簡単な機能から試したりするのもよいでしょう。負担が軽くなる成功体験を積み重ねていく工夫が求められます。
改善に非協力的なスタッフへの対処法は?
業務改善に非協力的なスタッフがいる場合、まず改善の本当の目的を共有しましょう。「今のやり方で問題ない」と考えているスタッフには、丁寧な説明が必要です。
「あなたの負担を軽くし、結果的に利用者へのケアの質も高めるため」という、本人へのメリットと組織の目標をセットで伝えると、協力が得やすくなります。
現場の意見を吸い上げる委員会を設け、そこで出たアイデアを改善策に反映させると、当事者意識が生まれます。一緒に職場を良くしていく仲間であるという意識を育てていきましょう。
予算がなくてもできる改善策はある?
大きな予算がなくても、業務改善を始める方法は多くあります。高価な機器の導入だけが業務改善ではありません。まずはお金をかけずにできることから着手しましょう。
業務改善の基本は、先にも解説したとおり「ムリ・ムダ・ムラ」を見つけて解消することです。たとえば、業務の手順書を作成して作業のばらつきをなくすなどの工夫は、すぐにでも始められます。
申し送りの時間を短くするために、情報共有のルールを決めるのも立派な改善です。国や自治体の補助金制度を調べてみるのもよいでしょう。小さな改善が、次の改善に進むための原動力になります。
まとめ
本記事では、介護現場に潜む7つの無駄な業務と、それらを解消するための改善の進め方を解説しました。日々の記録や会議に隠れた非効率を見直し「ムリ・ムダ・ムラ」の視点で課題を捉え、業務を棚卸しすることが改善の基本です。
小さな改善を積み重ねていくことは、職員の負担を軽くし、働きやすい職場環境の実現につながります。そうすれば、時間に追われることなく、一人ひとりの利用者とじっくり向き合う、本来あるべきケアの時間を取り戻せるはずです。
まずは1日の業務を10〜15分単位で書き出し、何に時間を使っているか「見える化」することから始めてみませんか。
防災⼠の詳細はこちら
証券会社勤務後、広告代理店兼防災用品メーカー勤務。経営管理部を立ち上げ、リスクマネジメント部を新たに新設し、社内BCP作成に従事。個人情報保護、広報(メディア対応)、情報システムのマネジメント担当。NPO事業継続推進機構関西支部(事業継続管理者)。レジリエンス認証の取得、更新を経験。レジリエンス認証「社会貢献」の取得まで行う。レジリエンスアワードとBCAOアワードの表彰を受ける。現在では、中小企業向けBCP策定コンサルティング事業部を立ち上げ、コーディネーターとして参画。
関連記事
-
介護施設
2026/01/23
冬の入浴介助の注意点|事故を防ぐ事前準備から緊急時の対応…

西條 徹
-
介護BCP
2026/01/16
地震のとき必要なもの|企業の備蓄義務・備蓄リスト・管理策…

西條 徹
-
介護施設
2026/01/09
介護施設のユニット目標例を紹介|目標作成の手順から振り返…

西條 徹
-
介護施設
2025/12/26
大量の書類の保管方法|監査で焦らない介護記録の整理術

西條 徹
-
介護施設
2025/12/12
新人教育で自分の仕事ができない!原因と3つの解決策を徹底…

西條 徹
-
介護BCP
2025/12/05
震度5弱と5強の違いは?5と6だけ弱・強がある理由から備…

西條 徹


