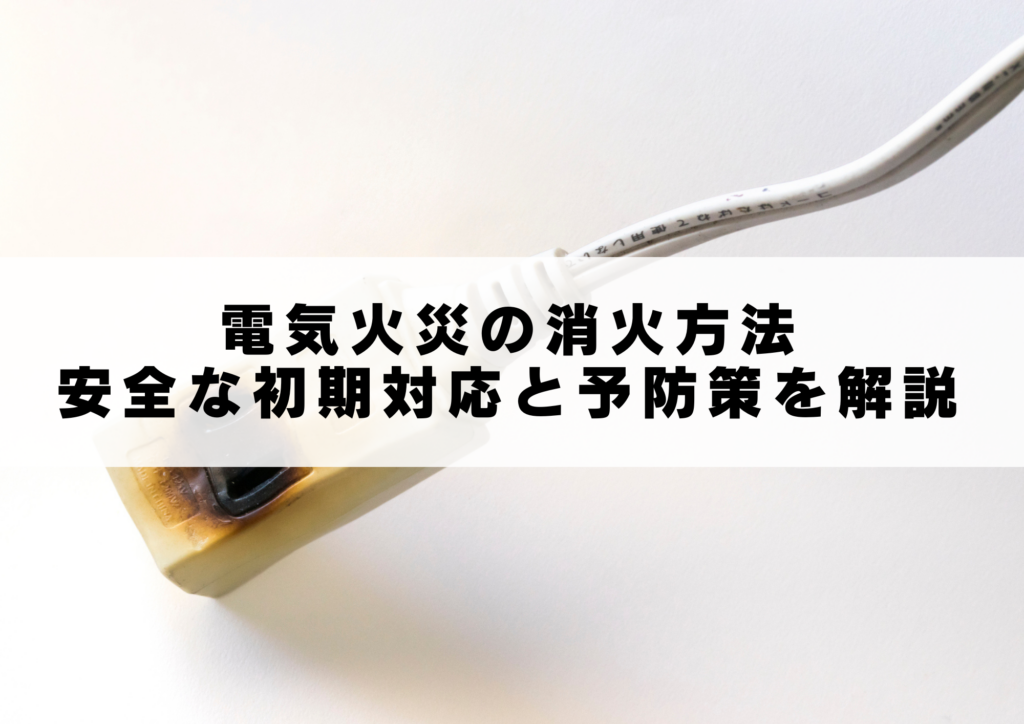
「パチッ」という異音と焦げ臭い匂い……。コンセントで怖い思いをした経験はありませんか?「もし本当に火事になったら?」「感電せずに消火できるのか?」と、お悩みではないでしょうか?
本記事では、いざというときの安全な消火方法から、日ごろからできる予防策、さらにはご家庭に合った消火器の選び方まで、あらゆる疑問に一つひとつお答えします。
この記事を読めば、もう電気火災のトラブルに慌てる必要はありません。ここで得た知識が、万が一の際にあなたとご家族を守るための、確かな備えとなるでしょう。
電気火災の安全な消火方法
足元のコンセントから異音がして焦げ臭い匂いがしたら、誰でもパニックになりますよね。
しかし、正しい手順を知っていれば、いざというときも冷静に対処できます。電気火災は、感電の危険があるため消火方法に注意が必要です。
これから、あなたとご家族の安全を守るための具体的な4つのステップを解説します。
1.まずブレーカーOFFで電源を遮断
電気火災が発生したら、何よりもまずブレーカーを落としてください。火災の原因である電気の供給を止めないと、火の勢いが強まったり、感電したりする危険があるからです。
安全が確保できるなら、火元となっている家電製品の電源プラグをコンセントから抜くことも有効な手段といえます。ただし、火や煙が迫っている状況では決して無理をしないでください。あなたの身の安全が第一です。
落ち着いて行動するために、ご自宅のブレーカーの場所を日ごろから確認しておきましょう。
2.119番通報と周囲への周知・避難路の確保
ブレーカーを落としたら、大声で「火事だ!」と叫んで、家族や周囲の人に危険を知らせましょう。初期消火が難しい場合に備え、消防への通報は不可欠です。可能であれば、誰かに119番通報を頼んでください。
通報の際は、落ち着いて住所や火災の状況を伝えましょう。また、消火活動を試みる場合は、必ず部屋の出口など避難できる経路を背にして火元に向かってください。
万が一の事態に備え、いつでも逃げられるようにしておくことが、ご自身の命を守ることに繋がります。
3.初期消火の判断と有効な道具・代替手段
火がまだ小さく、天井に燃え移る前であれば初期消火を試みてください。電気火災の消火では、水をかけるのは絶対にやめましょう。感電の恐れがあり非常に危険です。
電気火災には、電気を通さない性質を持つ専用の消火器が効果的です。特に、使用後の汚れが少ない二酸化炭素消火器や、幅広い火災に対応できるABC粉末消火器が推奨されます。
消火スプレーは手軽ですが、電気火災に対応しているか製品表示の確認が必須です。いざというときに慌てないよう、ご家庭に合った消火器を備えておきましょう。
4.鎮火後の安全確認と再発火のチェック
無事に火を消し止めた後も、決して油断はできません。完全に消えたように見えても、内部で火種がくすぶり続け、再び燃え出す「再発火」の危険があるからです。
特に、粉末タイプの消火器を使った場合は注意が必要です。消火剤はすべて使い切るつもりで、火元にしっかりと吹き付けてください。鎮火した後もすぐにその場を離れず、煙や異常な匂いがないか、しばらく様子を観察することが大切です。
コンセントが焦げている場合は専門業者に点検を依頼し、根本的な原因を取り除きましょう。
電気火災を未然に防ぐために
一度でもヒヤリとした経験をすると、火災そのものを起こさない対策が最も重要だと痛感しますよね。電気火災は、普段のちょっとした注意で防ぐことが可能です。
安心して毎日を過ごすために、火災の根本的な原因を理解し、ご家庭で今すぐできる予防策を具体的に見ていきましょう。
主な原因はホコリとコードの劣化
電気火災の主な原因は、実はとても身近な「ホコリ」と「コードの劣化」にあります。
コンセントとプラグの隙間に溜まったホコリが湿気を吸うと、電気がショートして突然発火することがあります。これが「トラッキング現象」です。
また、電源コードを束ねて使ったり、家具の下敷きにしたりすると、コードが傷んで異常に熱を持つ危険が高まります。普段あまり目の届かないテレビの裏や冷蔵庫の周りは、特に注意が必要です。
原因を知ることが、効果的な火災予防の第一歩になります。
自宅や職場の危険度チェック
ご自宅や職場に火災の危険が潜んでいないか、定期的にチェックする習慣をつけましょう。まず、一つのコンセントでたくさんの電化製品を使う「たこ足配線」は、過熱の原因になるため見直しが必要です。
次に、電源プラグがコンセントの奥までしっかり刺さっているか確認してください。ぐらついていると接触不良で熱を持つことがあります。
コードが家具に踏まれたり、強く折れ曲がったりしていないかも見てみましょう。もしコンセントに焦げた跡や変な匂いがあれば、それは危険のサインです。すぐに専門業者に相談してください。
今すぐできるコンセント掃除法
安全にコンセントを掃除するには、何よりもまず「ブレーカーを落とす」ことが大切です。感電やショートといった万が一の事故を防ぐため、必ず電源を元から断ってから作業を始めましょう。
ブレーカーを落としたら、掃除機やパソコン用のエアダスターなどでコンセント周りの大きなホコリを取り除きます。その後、乾いた歯ブラシや綿棒を使って、隙間にこびりついた細かい汚れを優しく取り除いてください。
最後に乾いた布で拭きあげれば完了です。水気のある道具の使用は、故障や火災の原因になるため絶対にやめましょう。
家庭に置くべき消火器具

万が一の火災に備え、ご家庭に消火器具を置くことは、家族の命と財産を守るための重要なお守りになります。ご家庭での設置は義務ではありませんが、初期消火の成否を大きく左右する大切な備えです。
いざというときに慌てないためにも、ご自宅に合った消火器具を選び、いつでも使えるように準備しておきましょう。
家庭用消火器の選び方
ご家庭に1本備えるなら、まずはいろいろな火事に使える「ABC粉末消火器」がおすすめです。このタイプは、木や紙の火災、油火災、そして怖い電気火災のすべてに対応できる万能さが魅力です。
購入の際は、国が安全性を認めた証である「検定マーク」や「NSマーク」が付いているかを必ず確認しましょう。また、住宅用消火器の使用期限は一般的に5年です。いざというときに使えないと意味がありません。
玄関や廊下など目につきやすく、すぐ手に取れる場所に置いて定期的に期限をチェックしましょう。
参考1:東京防災設備保守協会『煙式住宅用火災警報器製品紹介』
参考2:日本消防検定協会『消防機器』
参考3:社団法人日本消火器工業会『消火器読本』
消火スプレーの有効性と限界
手軽な消火スプレーは、あくまで本格的な消火器の補助的な役割と考えるのが良いでしょう。消火スプレーは法律上「簡易消火具」という位置づけで、消火器ほどの強力な消火能力はありません。
また、製品によっては電気火災に対応していないものも多く存在します。天ぷら鍋の小さな火のような、ごく初期の段階では有効です。
選ぶ際は、品質の証である「NSマーク」付きかを確認してください。もし電気製品に使うなら、必ずブレーカーを落としてから使用することが感電を防ぐための鉄則です。
電気火災に関するQ&A
電気火災への備えについて理解が深まると「こんなときはどうする?」という新たな疑問も生まれますよね。
ここでは、多くの方が気になるであろう具体的な質問にお答えします。いざというときに迷わず行動できるよう、細かい不安もここで解消しておきましょう。
消火器の使用期限は?点検は自分でできる?
ご家庭に置く消火器の使用期限は、おおむね5年が目安です。いざというときに使えないと意味がないため、ご自身で定期的に点検する習慣をつけましょう。
点検はとても簡単です。まず本体に記載された使用期限が過ぎていないか確認します。次に圧力計の針が緑色の範囲を指しているか、安全ピンが抜けていないか、容器にひどいサビやへこみがないかを目で見るだけで大丈夫です。
もし異常を見つけたら、すぐに専門業者に相談し、新しいものと交換してください。
スマホやモバイルバッテリーが燃え始めたらどうする?
もし充電中のスマホなどが燃え始めたら、まず慌てずにコンセントからプラグを抜いてください。
リチウムイオン電池の火災も電気火災と同じで、水をかけるのは感電の危険があり大変危険です。電気を止めたら、電気火災に対応している粉末(ABC)消火器や、機器を汚しにくい二酸化炭素消火器で消火します。
消火スプレーは電気火災に使えない製品が多いため注意が必要です。少しでも火の勢いが強いと感じたら、無理な消火はせず、すぐにその場から離れて安全を確保しましょう。
ブレーカーが落ちない、煙で近づけないときは?
ブレーカーを切りたいのに煙で近づけないなど、少しでも危険を感じた場合は、初期消火をすぐに諦めて避難してください。何よりも優先すべきは、あなたとご家族の命です。
煙は非常に危険で、吸い込むと動けなくなることもあります。ためらわずに大声で火事を知らせて家族を避難させ、すぐに119番通報しましょう。通報では住所と状況を正確に伝えます。
避難の際は、煙を吸わないよう姿勢を低くして出口へ向かうことが重要です。消火はプロである消防隊に任せましょう。
まとめ
今回は、突然襲ってくる電気火災に対して、どう対処し、どう防ぐかについてお伝えしてきました。
万が一の際は、慌てずブレーカーを切り、水を使わないこと。そして何より大切なのは、ホコリの掃除といった日ごろの備えで、火事を起こさないことです。
この記事を読み終えたら、ご自宅のブレーカーの位置と、テレビ裏のコンセントの状態だけでも確認してみてください。
その一手間が、電気火災の不安を「我が家は大丈夫」という安心に変えてくれるでしょう。
関連記事
防災⼠の詳細はこちら
証券会社勤務後、広告代理店兼防災用品メーカー勤務。経営管理部を立ち上げ、リスクマネジメント部を新たに新設し、社内BCP作成に従事。個人情報保護、広報(メディア対応)、情報システムのマネジメント担当。NPO事業継続推進機構関西支部(事業継続管理者)。レジリエンス認証の取得、更新を経験。レジリエンス認証「社会貢献」の取得まで行う。レジリエンスアワードとBCAOアワードの表彰を受ける。現在では、中小企業向けBCP策定コンサルティング事業部を立ち上げ、コーディネーターとして参画。
関連記事
-
介護施設
2026/01/23
冬の入浴介助の注意点|事故を防ぐ事前準備から緊急時の対応…

西條 徹
-
介護BCP
2026/01/16
地震のとき必要なもの|企業の備蓄義務・備蓄リスト・管理策…

西條 徹
-
介護施設
2026/01/09
介護施設のユニット目標例を紹介|目標作成の手順から振り返…

西條 徹
-
介護施設
2025/12/26
大量の書類の保管方法|監査で焦らない介護記録の整理術

西條 徹
-
介護施設
2025/12/12
新人教育で自分の仕事ができない!原因と3つの解決策を徹底…

西條 徹
-
介護BCP
2025/12/05
震度5弱と5強の違いは?5と6だけ弱・強がある理由から備…

西條 徹


