
台風が近づくたびに「出勤させてもいいのか」「ルールはどう決めればいいのか」と悩んでいませんか?
本記事では、台風時の出勤ガイドラインについて、法律の考え方や判断のポイント、従業員への伝え方、そして給料の扱いまでわかりやすく解説します。
この記事を読めば、従業員の安全を守りながらトラブルを防ぐ、会社としての正しい対応ができるようになります。どうぞ最後までご覧ください。
台風時に出勤させてもいい?
台風が近づいているとき「従業員に出勤してもらっていいのか」と迷う担当者は多いのではないでしょうか。
ここでは、出勤命令が法律的に問題ないのか、企業の責任として何に気をつけるべきかをわかりやすくお伝えします。まずは、出勤命令が法律上どう考えられているのか見ていきましょう。
出勤命令は法律的に問題ないのか
日本には、台風時の出勤を禁止したり、必ず休みにしたりする法律はありません。原則として、出勤させるかどうかは会社が個別に判断することになります。
ただし、法律には「安全配慮義務」という規定があります。これは「従業員の命や身体に危険がある状態で働かせてはならない」という考え方に基づくものです。
たとえば、強風や豪雨で電車の運休が予想されている中で無理に出勤させた結果、事故やけがが発生した場合、会社が責任を問われる可能性もあります。
出勤命令を出すか迷う場面では「従業員の安全が確保されているかどうか」を最優先に考えることが重要です。
安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、従業員の身体的・精神的な健康を損なわないよう配慮する義務です。これは労働契約法で定められており、すべての企業に求められる責任とされています。
この義務は、日常の業務だけでなく、台風や地震などの自然災害が起こりそうな場合にも適用されます。従業員が安全に過ごせるよう、会社として適切な配慮が求められます。
この義務を怠ると、損害賠償請求のリスクが生じるだけでなく、従業員の不満や離職の増加、採用難など、企業経営に悪影響を及ぼすおそれがあります。
台風時に限らず、さまざまな状況を想定し、安全に配慮できる体制を整えておくことが大切です。
参考:e-Gov法令検索『労働契約法』
ガイドラインがないと起こるトラブル
ガイドラインがなく、出勤すべきかどうかの判断を従業員に委ねてしまうと、行動にばらつきが出てしまいます。
また、出勤しなかった従業員への対応も不明確になり「休んだら給与はどうなるのか」「評価に影響するのか」といった不安を招く可能性があります。その結果、無理をしてでも出勤しようとする従業員が出てくるかもしれません。これでは、かえって会社のリスクが高まります。
「安全配慮義務を果たしていない」と思われる状態が続けば、従業員との信頼関係も損なわれてしまうでしょう。だからこそ、台風などの自然災害に備えて、出勤に関するガイドラインを明確に整備する必要があります。
ルールを定めておけば、従業員も安心して行動できますし、会社としての責任も果たせます。誰が見てもわかる判断基準や連絡方法をあらかじめ決めておきましょう。
台風時の出勤ガイドラインの作り方
ここからは、出勤・休業・在宅勤務の判断基準の設け方、気象情報との連動方法、従業員への伝え方など、台風時の出勤ガイドラインの作り方を解説します。
まずは、判断基準をどのように決めればよいかを見ていきましょう。
出勤・休業・在宅の判断基準の考え方
出勤するかどうかの判断で最も重要なのは「従業員の命を守る」という視点です。そのためには、感覚的に判断するのではなく、あらかじめ明確な基準を設けておく必要があります。
まず注目すべきは、天候や交通の危険度です。たとえば、台風の強さや交通状況に応じて「通常通り出勤」「安全を確認した上で出勤」「在宅勤務」「自宅待機」といった段階を設定し、それぞれの段階での対応を整理しておきましょう。これにより、従業員が迷わず行動できるようになります。
リモートワークが可能な職種であれば、災害時はできるだけ自宅で勤務してもらうのが安全です。ただし、自宅勤務も困難な状況であれば、休業を指示する判断も必要です。休業とする際は、給与の取り扱いに関するルールもあわせて定めておきましょう。
また、事業所の立地や業務内容によって判断基準が変わることもあります。たとえば、海や川の近くにある会社や、医療・介護など社会的に業務を止められない職種には、それぞれに応じた柔軟な対応が求められます。
気象情報・交通状況と連動させる方法
ガイドラインを作成する際には、気象や交通の情報を判断の根拠とする仕組みづくりが重要です。情報源としては、気象庁の公式サイトや交通機関のホームページなどを活用しましょう。
情報を確認するだけでなく「誰が」「いつ」「どの情報をチェックして」「どこに報告するのか」といったルールも決めておくと安心です。さらに「前日の17時」「当日の朝6時」など、判断のタイミングもあらかじめ定めておくとよいでしょう。
天気や交通の状況は時間とともに変化するため、判断の機会を1回に限らず、2回目の確認タイミングを設けておくと、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。最近では、リアルタイムで道路や鉄道の運行状況を確認できるサービスもあります。
情報とルールを連動させることで、判断の基準が明確になり、従業員の納得感も高まります。
従業員へのわかりやすい伝え方
せっかく良いルールを整えても、従業員に正しく伝わらなければ意味がありません。ガイドラインは「読んだ人がすぐに行動できる」ことを意識して伝えることが大切です。
まずは、難しい言葉を避け、誰でも理解できる表現を使いましょう。また「暴風警報が出たら原則在宅勤務」など、結論を先に示すことで、内容がより伝わりやすくなります。その後に説明を加えると、より理解しやすくなります。
さらに、判断基準、連絡方法、よくある質問などを見出しごとに整理すると、情報が整理されて伝わりやすくなります。
伝達手段も重要です。メールや社内ポータル、チャットなど、普段から使っているツールを活用し、全従業員に確実に情報を届けましょう。
また、ガイドラインを作成したら説明会を実施するのも効果的です。資料を配布したり、質問を受け付けたりすると、より従業員の理解が深まります。緊急時の訓練を行い、実際に動いてみるのも有効です。
以下の記事では台風が来た時の対策について詳しく説明しております。
出勤できなかったら給料はどうなる?
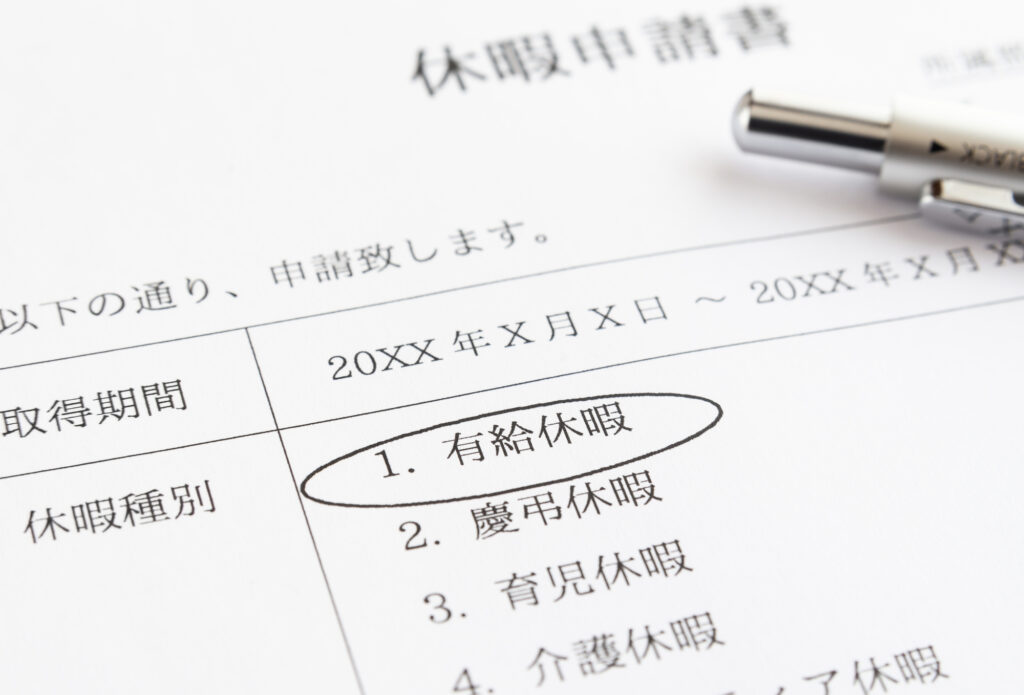
台風の日に会社を休んだとき「その日の給料は出るのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。実は、給料が出るかどうかは、休んだ理由や会社の指示があったかどうかで変わってきます。
ここでは、その考え方とあわせて、休業手当や有給、無給の使い分けについても説明します。まずは、会社都合と自己都合の違いから見ていきましょう。
会社都合・自己都合の違いとは
会社を休んだときに給料が支払われるかどうかは「誰の判断で休んだのか」によって異なります。会社の指示で休む場合と、自身の判断で休む場合では、取り扱いが異なります。
会社の都合で休業の指示があった場合は「会社都合」となります。この場合、会社には休業手当を支払う義務があり、平均賃金の60%以上を支給しなければなりません。
一方、従業員の判断で休んだ場合は「自己都合」とされます。この場合「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、その日の給料は支払われません。月給制であっても、欠勤分が差し引かれることになります。
台風などの自然災害時には、判断が曖昧になることもあります。そのため、会社として出勤に関するガイドラインを整備し「会社都合かどうか」を従業員に明確に伝えることが重要です。
休業手当・無給休暇・有給休暇の使い分け
会社を休んだ場合の給与の扱いには、いくつかのパターンがあります。出勤しない日が「休業手当」「無給休暇」「有給休暇」のいずれに該当するのかを明確に区別しておくことが重要です。
まず「休業手当」は、会社都合で休業するよう指示した場合に支払われるものです。たとえば、台風により会社が「今日は出社しなくてよい」と決めた場合などが該当します。労働基準法第26条により、平均賃金の60%以上を支払うことが義務付けられています。
次に「無給休暇」は、給与が発生しない休みのことを指します。有給休暇を使い切った場合や、法律で取得が認められているが給与の支払い義務がない休暇(生理休暇、育児休業など)も含まれることがあります。また、会社が独自に設定している休暇(夏季休暇や慶弔休暇など)についても、無給となるかどうかは会社の規定次第です。
最後に「有給休暇」は、休んでも給与が支払われる法定の休暇です。年10日以上の有休が付与されている従業員については、会社が年5日以上の取得を義務づけられています。従業員が有休の取得を希望した場合、会社がそれを無給扱いにすることはできません。
このように、休暇の理由や内容によって給与の扱いは異なります。従業員から「本日の休みの扱いはどうなるのか」と尋ねられたときに、すぐに説明できるよう、事前に社内ルールを整備しておきましょう。
参考:厚生労働省『労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について』
よくある質問(Q&A)
台風が近づくと「休んでもいいのか」「給料はどうなるのか」といった不安を感じる方も少なくありません。とくに会社から明確な指示がない場合、判断に迷うことも多いでしょう。
ここでは、よくある質問の中から、実際にトラブルになりやすい内容を取り上げてお答えします。
自己判断で休んだら欠勤扱いになる?
会社から休んでよいという明確な指示がないまま、自分の判断で出勤を見合わせた場合、その日は原則として欠勤扱いとなります。給料は支払われず、人事評価に影響する可能性もあります。
労働契約上、出勤日は原則として出社する義務があります。たとえ台風であっても、会社が出勤可能と判断している場合には、自己判断での欠勤は就業規則に反すると判断されることがあります。
ただし、会社の指示が曖昧だったり、通勤に身の危険を感じたりする場合には、まず会社に連絡して指示を仰ぐことが大切です。トラブルを避けるためにも、事前に明確なガイドラインを整備しておくことが望まれます。
電車が止まったらどうすればいい?
まずは会社に連絡し、出勤が難しい旨を伝えて、指示を仰ぎましょう。バスやタクシーなど代替手段の利用を求められることもありますが、危険がある場合には、無理に出勤する必要はないでしょう。
在宅勤務や自宅待機の指示が出ることもありますが、その際の給与の取り扱いは会社のルールによって異なります。天災による休業では、給与が支払われない場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、電車の遅延や運休があった場合は、遅延証明書を取得しておくと、後の説明が円滑になります。安全を最優先に、冷静に対応するようにしましょう。
まとめ
台風の接近時に出勤させてもよいのか迷ったとき、もっとも大切なのは社員の安全です。この記事では、法的な考え方から具体的な判断基準、社員への伝え方、給与の扱いまでを整理してお伝えしました。
ガイドラインを明文化しておくことで、判断の迷いをなくし、現場の混乱や労務トラブルを防ぐことができます。
まずは「気象情報と交通状況をもとに、いつ誰がどう判断するか」を社内で話し合い、シンプルな基準から作ってみましょう。備えがあれば、どんな天候でも落ち着いた対応ができ、社員との信頼関係も強まります。
関連記事
防災⼠の詳細はこちら
証券会社勤務後、広告代理店兼防災用品メーカー勤務。経営管理部を立ち上げ、リスクマネジメント部を新たに新設し、社内BCP作成に従事。個人情報保護、広報(メディア対応)、情報システムのマネジメント担当。NPO事業継続推進機構関西支部(事業継続管理者)。レジリエンス認証の取得、更新を経験。レジリエンス認証「社会貢献」の取得まで行う。レジリエンスアワードとBCAOアワードの表彰を受ける。現在では、中小企業向けBCP策定コンサルティング事業部を立ち上げ、コーディネーターとして参画。
関連記事
-
介護施設
2025/12/26
大量の書類の保管方法|監査で焦らない介護記録の整理術

西條 徹
-
介護施設
2025/12/12
新人教育で自分の仕事ができない!原因と3つの解決策を徹底…

西條 徹
-
介護BCP
2025/12/05
震度5弱と5強の違いは?5と6だけ弱・強がある理由から備…

西條 徹
-
介護施設
2025/11/26
処遇改善加算を基本給に含むのは違法?導入の7ステップと運…

西條 徹
-
介護施設
2025/11/19
超音波式加湿器は意味ないって本当?介護施設でのリスクと安…

西條 徹
-
介護施設
2025/11/05
コンセントのほこり火事を防ぐ!高齢者宅の危険箇所と掃除の…

西條 徹


